(本記事は広告リンクを含みます)
ムンク展の開催初日、ノルウェー・ムンク美術館展覧会及びコレクション部長のヨン・オーヴェ・スタイハウグ先生の講演が行われました。講演を聞いて分かったのは、今回来日しているムンク作品の見るべきポイントは、彼が作品を作るにあたって行ったさまざまな「実験」ということ。講演で触れられていたムンクの実験の数々、あらかじめ知っておいてから会場に行くとより展覧会が楽しめそうなので、下記にまとめておきます。
1. ムンクの実験:批判的評価と支援者たち
ムンクの作品は当初、保守層(特にブルジョワ層)から下記のような批判を受けていたそうです。

しかし、このような表現はムンクが製作活動の中で行った実験であり、新たな表現を生み出すためのプロセスだったということです。それを理解してくれたのが、師匠や支援者となってくれた芸術家たちでした。ただし、そういった理解者からも、ムンクが行った実験的手法は「やりすぎだ」とコメントされることもあったのだそうで、当時、いかにムンクの実験が斬新なものであったかがよく分かるエピソードだと思います。ムンクは、同じモチーフの作品を何度も製作することで実験を繰り返しており、それらを展覧会会場で比較してみる、ということがひとつの見どころです。
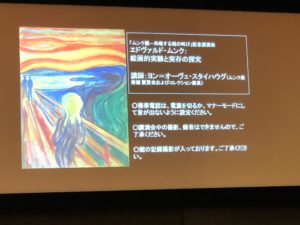
ムンク展:特別講演開始前の様子。やはり代表作は「叫び」
講演では、ムンクは創作活動の中で下記のような実験をしていると示されていました。
①色彩の強度、塗り方、筆遣いの実験
- 絵の具をわざと厚塗りにする→力強さや荒さを出す
- 絵の具をブロックのように積み上げて塗り、凸凹感を出す
- 薄い絵の具で、あえてキャンバスの地色が透けるように描く→画面に透明感を出す
- 絵の具を載せた後、削る・描きなおすを繰り返し、画面に引っかき傷を残す→荒い仕上がりにすることで、強い感情を示す
- キャンバスに何も塗ってない部分を残す
- スプレーのような絵の具の塗り方
- 垂直と水平の線だけで描く
- あえて絵の具が垂れるようにする
②版画の実験的手法
- 版画の表面に引っかき傷をつける
- 版木の木目も作品内に表現する
- 仕上がった版画の表面に、さらに絵の具で描く
③感情、欲求、自然の力を画面に表現する
- 上記①②の各種手法を組み合わせて、人間の感情や欲求をよりドラマチックに表現する
- 誇張された遠近法を使って画面の中に鑑賞者を引きずり込み、鑑賞者の感情に直接訴える
③についてはまだわかりますが、①や②は何も知らない人が見れば「未完成で雑な作品だ」、「急進的すぎて理解できない」と思ってしまうのも一理あるような気がします。しかし、当時はなかなか受け入れられなかったムンクの実験こそが、彼の作品の中に人の心を揺さぶるような効果を生み、後世に名を刻むことになったのです。
次に、これらの「実験」がよく分かる展覧会作品についてまとめたいと思います。
2. ムンク展で見られる実験の数々
今回のムンク展は、第1章~第9章までの各セクションに分かれ、101作品が展示されています。すべてがムンクの作品です。各章の構成は下記のようになっています。
2章:家族ー死と喪失ー
3章:夏の夜ー孤独と憂鬱ー
4章:魂の叫びー不安と絶望
5章:接吻、吸血鬼、マドンナ
6章:男と女ー愛、嫉妬、別れ
7章:肖像画
8章:躍動する風景
9章:画家の晩年
各章で見られる実験的手法を、具体的な作品名を挙げて見ていきたいと思います。カタログNo.は、本展の出品作品リストに掲載されている番号です。展覧会場で入手できます。
1章:ムンクとは誰か
自画像(1895年):カタログNo.1

自画像(1895年)
リトグラフで製作された作品で、正面を向いたムンクの頭部が描かれています。頭部以外は黒インクで体は闇に埋もれており、黒い表面には白い線が見えますが、これは引っかき傷がつけられているのだそうです。ガイコツの上腕部が画面下部に横たわっていますが、これは死の象徴で、ムンクの生死に対する強い関心を示しているとのこと。また、画面上端部の署名はアルファベットが裏返しに書かれており、これも実験のひとつと言えるかもしれません。
2章: 家族ー死と喪失
死と春(1893年):カタログNo.17
ムンク展公式サイトに画像があります↓
https://munch2018.jp/gallery/#&gid=1&pid=8
画面手前のベッドに死者が横たわっており、手前側の画面は全体的に暗い色調となっています。一方、窓の外は新緑を思わせる明るい緑色で、新たな生命の活力がみなぎる春を描いており、生と死のコントラストを表現することで死に際しての強い感情の揺さぶりをドラマティックに描いています。
「病める子」モチーフの連作:カタログNo.20〜22
- 病める子(1894年):カタログNo.20
- 病める子 Ⅰ(1896年):カタログNo.21
- 病める子 Ⅰ(1896年):カタログNo.22

病める子 Ⅰ(1896年)
ムンクは、病に臥せっている子供、時にはその家族を描いた連作を残しています。今回はそのうちの3点が来日。ムンクは死を身近に感じる経験をしており、特に姉を結核で亡くしたことがこの「病める子」製作の動機となりました。姉の死の本質を捉え、その悲しみに対応するために製作した一面もあるそうです。「病と狂気と死が、私の揺りかごを見守る黒い天使たちだった」との言葉を残しており、ここからも生と死に対する強い関心が伺えます。連作を通じて様々な実験を行っていたようなので、その点も会場で要チェックです。
3章:夏の夜ー孤独と憂鬱
夏の夜、声(1896年):カタログNo.36
ムンク展公式サイトに画像があります↓
https://munch2018.jp/gallery/#&gid=1&pid=22
夏の夜を描いた木版画です。垂直に描かれている雑木林の向こうには海面が描かれています。おそらく、空には月が浮かんでいるのですが、月そのものは描かれておらず、月の光がぼうっと垂直方向に海面に反射していることで月の存在を推し量ることができます。正面にはひとりの女性が描かれていますが、その表情を読み取ることはできず、どんな感情を抱いているのかは推測するしかありません。海面は水平方向の滑らかな線で彫られているのに対し、雑木林の木・月光・雑木林の手前の草地は鋭い垂直の線で描かれており、対比的な効果を生んでいます。実験的な要素と思われるのは、女性の顔面から首筋にかけて細かい垂直方向の線(傷のように見えます)があること。絶望、愛、欲望などが表現されているのかもしれません。
4章:魂の叫びー不安と絶望
叫び(1910年?):カタログNo.46

「叫び」(1910年?)
超有名な「叫び」が初来日です。必見ですね。「叫び」のモチーフは4枚描かれており、1910年のバージョンのみが今回日本に来ています。「叫び」は数々の下絵、スケッチを経て1年以上かけ捜索したモチーフなのだそうです。これは厚紙に描かれていますが、厚紙で製作するということ自体も実験なのだとか。ムンク自身の言葉によれば、夕暮れ時に友人と歩いていてふと不安を感じ空を見ると、日没の空が血の色のように赤く染まっており、自然から叫びが聞こえたということが製作のきっかけになったとのこと。この作品においてムンクが挑戦しているポイントは、「聴覚を視覚で表現する」ということ。聞こえてきた叫びは聴覚ですが、それを絵画=視覚という形で表現することは、確かに大きなチャレンジですね。スタイハウグ先生は、叫びには2つの解釈があるとおっしゃっていました。
- 叫びが自然のあらゆる場所から聞こえたため、自分自身が苦痛や苦しみを感じている様子を描いている
- 自分自身の心の叫びを自然に投影して描いている
会場で実物を見て、どちらの解釈が正しいかなと考えたり、また、もっと別の解釈があるのでは?と想像するのも見どころですね。
5章:接吻、吸血鬼、マドンナ
「接吻」モチーフの連作:カタログNo.50-54
- 接吻(1897年):カタログNo.50
- 月明かり、浜辺の接吻(1914年):カタログNo.51
- 接吻(1895年):カタログNo.52
- 接吻Ⅱ(1897年):カタログNo.53
- 接吻Ⅳ(1902年):カタログNo.54

「接吻」(1902年)
男女が抱き合ってキスしている様子を描いている連作です。やわらかい線で包み込まれるような形で男女が描かれており、幸福感が伝わってくるのですが、ちょっと怖いのが2人の境目が不明瞭になっていること。両者がとけあってしまっていて、どこからが男性の体で、どこからが女性の体なのかがよく分からず、お互いが依存しあっているような不気味さを感じます。男女の愛情の幸福な面と、その反面、愛情ゆえに個を失うような怖い面両方を描いているのかもしれません。接吻の実験的要素は、人物をやや抽象的に描くことと、1902年のバージョン(上の画像)では、版画の木目を最終的な作品に背景として配置していることだそうです。
6章:男と女ー愛、嫉妬、別れ
マラーの死(1907年):カタログNo. 74

「マラーの死」(1907年)
題材となっている出来事は、フランス革命の指導者ジャン=ポール・マラーが対立勢力の女性に暗殺された事件です。ベッドに暗殺されたマラーが横たわっており、そのベッドの前に暗殺の実行犯である裸の女性が鑑賞者の方を向いて、直立不動で立っています。ここで行われている絵画的実験は、厚塗りのパステルをざっとスケッチするときのような荒っぽい筆遣いで使用し、悪夢のような状況を表現していることだそうです。特に、垂直と水平の線だけで画面を構成することは非常に大きなチャレンジであるのだとか。
すすり泣く裸婦(1913-14年):カタログNo.76

「すすり泣く裸婦」(1913-14年)
赤と緑色で描かれたベッドの上に、長い髪を振り乱した裸婦が座っていて、両手で顔を押さえて嗚咽しています。裸婦の表情は長い黒髪に隠れていて、伺い知ることはできません。この作品での実験的試みは、筆遣いを強くし、荒々しい描き方をすることで裸婦の感情を描き、絵の具を建物を建設するブロックのように積み上げたり、キャンバスの一部を塗らずに残したり、絵の具をあえて垂れさせたりしていることで、大変急進的な実験を採り入れた作品だそうです。
8章:躍動する風景
太陽(1910-13年):カタログNo. 89

「太陽」(1910-13年)
20世紀になってムンクの作品のテーマは変化し、生命を肯定する、活力のあるイメージを表現するようになりました。この作品は、オスロ大学の講堂の絵として依頼されて製作されたもので、手前の二つの山の向こうに水面と遠い山々の稜線が描かれ、その稜線の上方に太陽が光り輝いている様子です。太陽光は非常に強く描かれ、光の広がりは画面手前の山だけでなく、鑑賞者の方まで到達してくるような勢いを感じます。太陽は全ての生命の源であり、自然の力をいかに力強く描くかということに挑戦しているのかもしれません。
会場で実物を実際に見た際、画像とのギャップが最も大きかったのはこの作品でした。放射状に広がる太陽光のうち、太陽の中心に近い部分はキャンバス上で太く盛り上がっており、絵の具のチューブから直接キャンバスに絞り出したような力強い線となっており非常にインパクトが強かったです。太陽光は端に行くほど載せられた絵の具量が少なくなり、最後画面の端に到達する頃にはかすれた線となっており、中心部と全く異なる線の描き方になっています。実物でないとこの力強さは実感できないので、ぜひ会場でチェックしてみてください。
9章:画家の晩年
自画像、時計とベッドの間(1940-43年):カタログNo. 101

「自画像、時計とベッドの間」(1940-43年)
晩年のムンクが描いた自画像で、自分の死に直面している様子が描かれています。画面左から順に時計=時間、自分自身、ベッド=死が並んでおり、自分自身が時計とベッドの間にいる=死がまもなく訪れることを暗示しています。一方で、活力を表す表現も見受けられ、例えば背景の壁面にある裸婦像や、ベッドカバーの赤と黒のリズミカルなパターンが該当します。死の意識と、活力=生へのこだわりが示されているのかもしれません。この布のパターンに絵の具や鉛筆を使用して独特な質感を出していることが一つの実験的要素なのだそうです。
まとめ
スタイハウグ先生の講演から、ムンクが周囲の批判にもめげず、数々の実験を繰り返しながら新しい表現を模索していったということがよくわかり、大変勉強になりました。有名な「叫び」だけではなく、今回はムンク作品101点が来日しており、彼の行った実験を数多く目にすることができる貴重な機会だと思います。ここで紹介した以外にも、様々な実験があるかもしれませんので、会場で実物を観察してみて、あれこれ想像するのも楽しそうです。
ムンク展の訪問レポートを、下記の記事に書いています。「叫び」を鑑賞するにあたって、整列ルールがあったのでそれをまとめました。これから行かれる方はチェックしてみてください↓











・前衛的すぎる